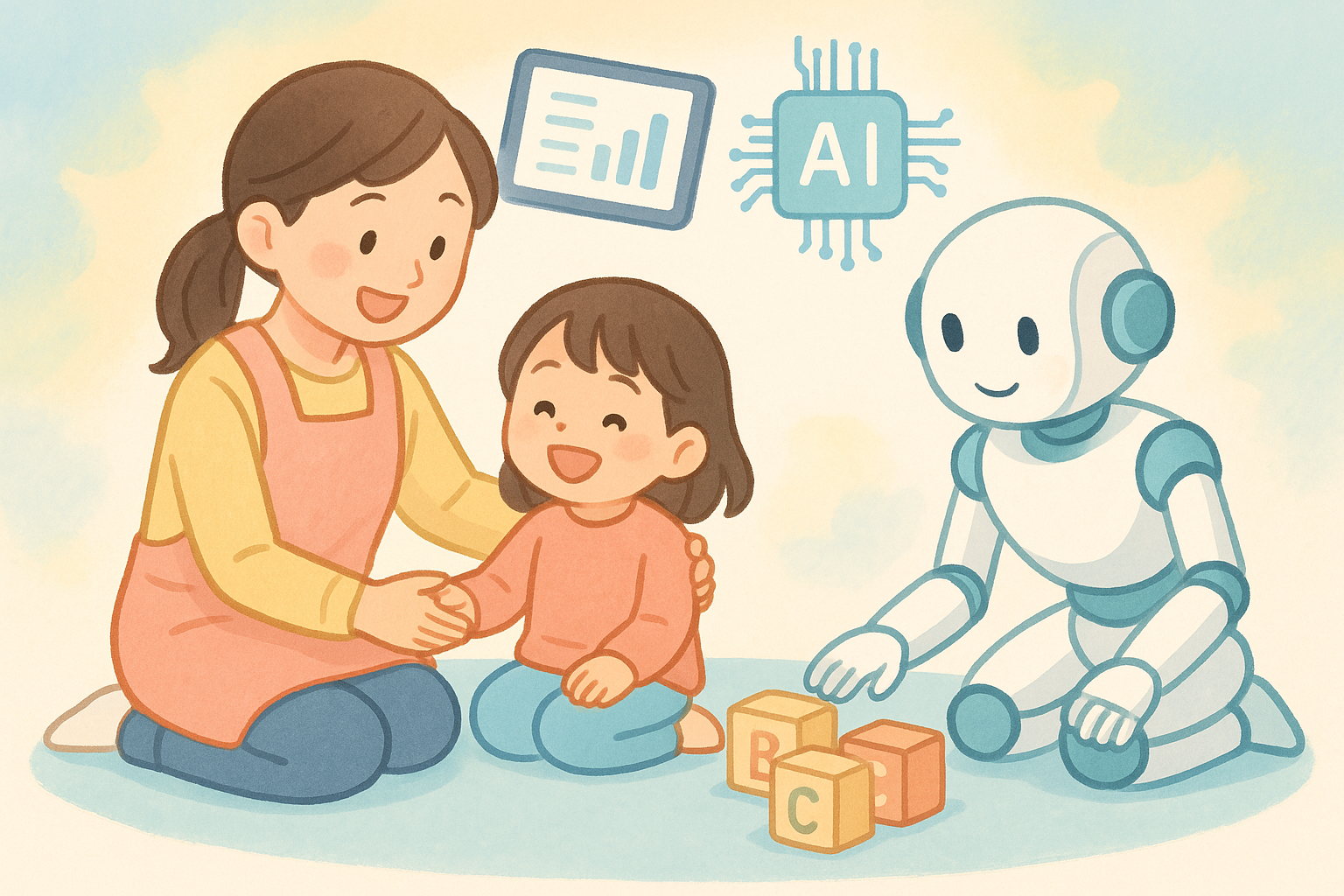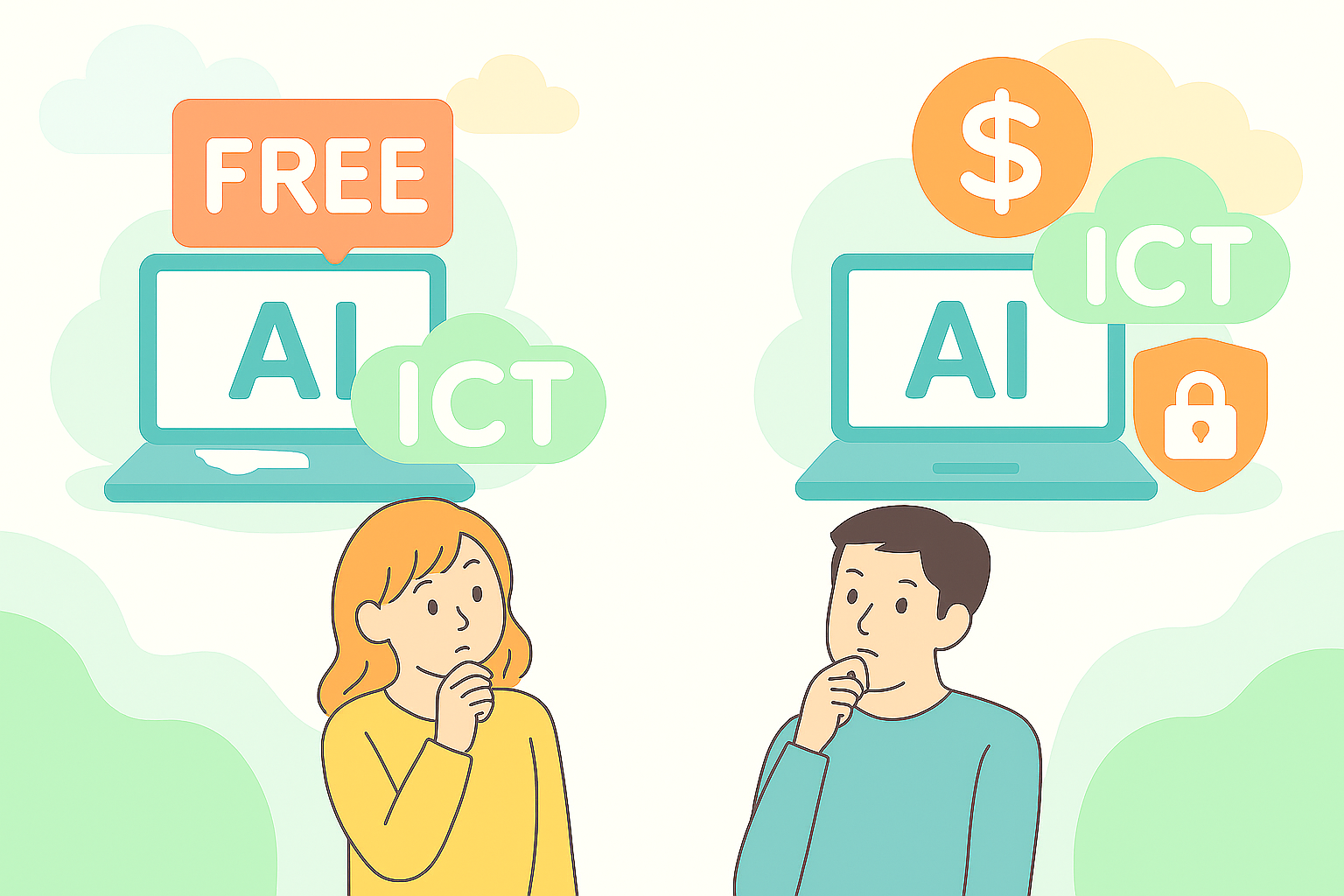AIやICTが進化し、保育現場でもテクノロジーの活用が当たり前になってきている現在。そんな時代において、私たち保育士にはどのようなスキルが求められるのでしょうか。そして、どんなに時代が変わっても、保育士として変わらず大切にしたいことは何でしょうか。ここでは、それらのことについて、一緒に考えていきたいと思います。
AI時代に求められる保育士のスキル
- テクノロジーを活用するスキル(デジタルリテラシー)
- AIやICTツールを効果的に使いこなす基本的な操作スキル。
- 新しいツールや情報を自分で調べ、学ぶ力。
- インターネット上の情報の真偽を見極める力(情報リテラシー)。
- セキュリティ意識を持ち、適切に情報を扱えること。
- AIが出した情報を吟味し、活用する力(クリティカルシンキング)
- AIが生成した文章やアイデアを鵜呑みにせず、それが本当に適切か、子どもたちの実態に合っているかなどを批判的に考え、判断する力。
- AIの提案をヒントにしつつ、自身の経験や知識と組み合わせて、より良い形に発展させる応用力。
- AIと協働するためのコミュニケーション能力
- AIに対して、的確な指示(プロンプト)を出し、期待するアウトプットを引き出す力。
- AIとの対話を通じて、より良い解決策を見つけ出す力。
- 変化に対応する柔軟性と学び続ける意欲
- テクノロジーの日々の進化に合わせ、新しい技術や考え方を柔軟に受け入れ、積極的に学び続ける姿勢。
- 試行錯誤を恐れず、新しいやり方にチャレンジする意欲。
- 倫理観と責任感
- AIを利用する上で、個人情報保護や著作権などのルールを遵守する倫理観。
- AIの判断を参考にしつつも、最終的な判断と行動には保育士自身が責任を持つという意識。
これらのスキルは、特別なものではなく、これからの社会で働いていく上で共通して求められるものでもあると考えます。少しずつ、できることから身につけられるといいですね。
変わらない、保育士として大切にしたいこと
テクノロジーがどんなに進化しても、保育の中心は「人」であり、「子ども」です。AIには代えられない、保育士だからこそできる大切な役割があります。以下に、その役割についていくつかあげていますが、これらはほんの一部でしかありません。”保育士としての価値”は、ここで言うまでもなく、現場の皆さん一人ひとりが、身に染みて分かっていることだと思います。ここでは、AIという文脈の中で語られる話の一部として、お読みください。
- 子ども一人ひとりと向き合う温かい心、愛情
- 子どもたちの小さな変化に気づき、その気持ちに寄り添い、共感する心。
- 一人ひとりの個性を尊重し、無条件の愛情を注ぐこと。
- 抱きしめたり、手をつないだりといった、温かい肌の触れ合い。
- 子どもの発達を理解し、寄り添う専門性
- 乳幼児期の発達段階や特性を深く理解し、一人ひとりの成長に合わせた適切な援助を行う専門知識と技術。
- 子どもたちの「やってみたい」という主体性を引き出し、あそびを通して学びを深める環境構成。
- 観察力、共感力、人間同士のコミュニケーション能力
- 言葉にならない子どもたちの思いを表情や行動から読み取る観察力。
- 保護者や同僚と円滑なコミュニケーションを取り、信頼関係を築く力。
- 子どもたちの葛藤や喜びを共に感じ、分かち合う共感力。
- 人間ならではの創造性、倫理観、生命への畏敬の念
- 子どもたちの自由な発想を大切にし、共に新しいものを生み出す喜び。
- 命の尊さや、人として大切なことを子どもたちに伝えていく役割。
- 日々の保育の中で、豊かな感性や表現力を育むこと。
- 保護者との信頼関係構築と子育て支援
- 保護者の不安や悩みに寄り添い、共に子どもの成長を喜び合う”パートナーシップ”としての役割。
- 家庭と連携し、子育てを社会全体で支えていくという視点。
AIは、私たち保育士の業務を効率化し、時間的なゆとりを生み出してくれる素晴らしいツールです。そのゆとりを、子どもたち一人ひとりとじっくり関わる時間や、保育の専門性を深めるための時間にあてることで、保育の質はさらに高まっていくはずです。
テクノロジーを恐れるのではなく、賢く味方につけて、私たち人間だからこそできる温かい保育、創造的な保育を、これからも大切にしていきたいですね。
2025年現在、写真・動画・日々の連絡ノートや定期的に配信・配布されるおたより、中には一人ひとりの記録をドキュメンテーションで収め、保護者も見られるようにしている園もあるようです。筆者が新人保育士で、ブログやSNS、動画配信などの様々な発信方法が少なく、紙面で伝えるのが主流だった頃、先輩からの言葉で今でも忘れられないものがあります。
「記録をとるために保育をするんじゃなくて、保育をするために記録をとるんだよ」
「保護者への連絡ノートやおたよりは、保育への理解や協力のためにやってることなんだよ」
この言葉が今になって思い返されるのは、以下のことを危惧してのことです。
○記録をとるための保育になっていないか?
○園のブランディング(広告)に偏り、保育がおざなりになっていないか?
○撮影に集中するあまり、その後ろで、子どもがケガになりそうになったことはないか?
様々な発信方法がある現在、
「そもそもなんで発信しているのか」
「その発信方法でなければいけない理由はなにか」
「発信内容が他のものと重複して業務過多になっていないか」
「発信に重きを置きすぎることで、保育に支障は出ていないか」
…等々、発信のあり方については、いろいろと考えさせられるものがあります。
もちろん、保護者からは喜ばれますし、就活生を呼び込む上でも重要な役割を担っていて、そこのメリットも承知しています。ただその一方で、子どものためというよりも、保護者のため、就活生のため、園をより良く見せたいという”見栄”のために傾きすぎて、いつの間にか”発信だけが目的の保育になっていないか”という視点も、非常に重要なことだといえるでしょう。
こうした問題は発信方法に限らず、他の様々な場面にもあり、「なぜ(=保育の意図・意味)」の視点は、これまでに述べてきた「保育士として大切にしたいこと」にも含まれているもので、保育の質について考える上でも、とても大切なことだと思います。
ブログ、SNS、動画配信など、これらはあくまでも【手段】であることを強く意識し、その上で、各園で大切にしている”軸”を、本当の意味で共有した保育が実践できるといいですよね。