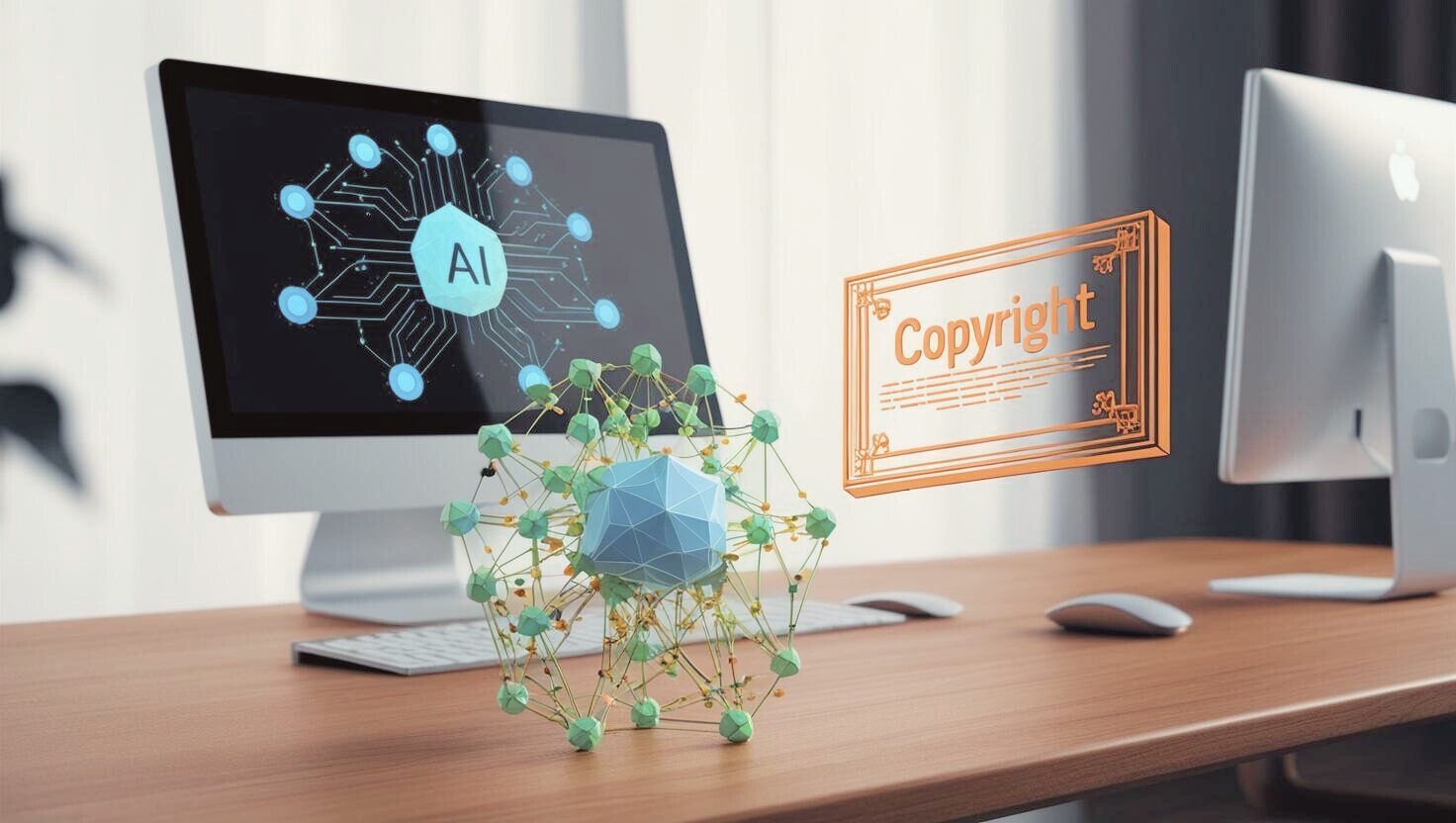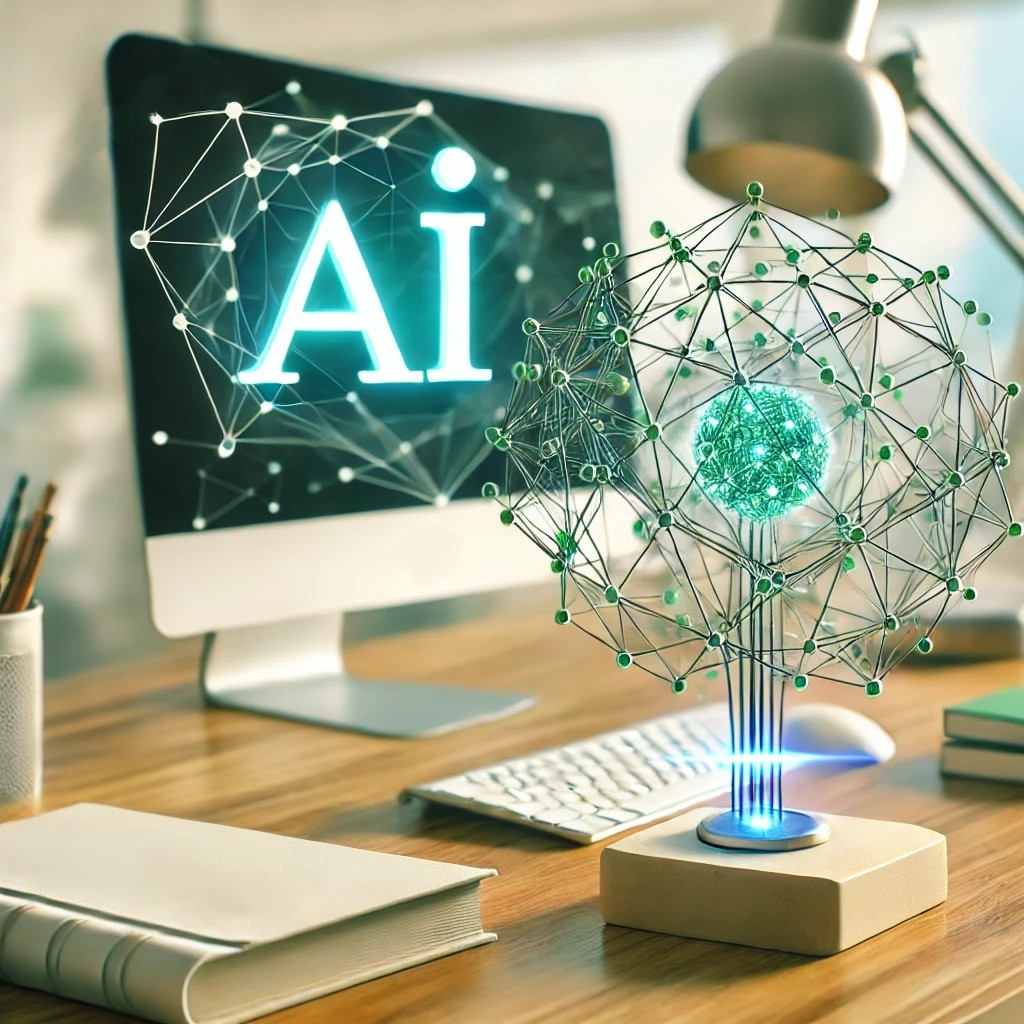生成AIに対して不安がある人の多くは、
【入力したデータが収集・学習されていないか】
【出力された結果の正確性・信憑性の懸念】
【生成AIの事前学習データが著作権等に違反していないか⇒そのまま利用してもいいのか】
…と、おおまかにこれら3つの不安があるかと思います。
これらの不安解消のため、【正しい生成AIの知識と使い方】を以下に紹介します。
入力したデータの取り扱いについて
①生成AIに入力した個人情報やプライバシーに関する情報が生成AIの機械学習に利用されることがあり、生成AIから回答として出力されるリスクがある。また、AIが生成した回答に不正確な個人情報やプライバシーに関する情報が含まれるリスクもある。
② 上記の点を踏まえ、学校教育においては、子供達が校内や家庭で利用する場合、教職員が授業や校務等で利用する場合のいずれにおいても、以下の点に留意することが必要。
生成AIに指示文(プロンプト)を入力する際は、個人情報やプライバシーに関する情報を入力しない。(以下省略)令和5年7月4日 文部科学省 初等中等教育局
『初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン』より一部抜粋
『入力する際は、そもそも個人情報やプライバシーに関する情報を入力しない』
…と、ここに尽きます。
厳密に言うと、学習に利用しないことを謳っている生成AIや、情報を取得しないよう設定から変える方法もありますが、多忙を極める保育者の皆様には、この方法がベストだと考えます。
出力結果の正確性・信憑性について
これらのAIは、あらかじめ膨大な量の情報から深層学習によって構築した大規模言語モデル
(LLM(Large Language Models))に基づき、ある単語や文章の次に来る単語や文章
を推測し、「統計的にそれらしい応答」を生成するものである。指示文(プロンプト)の工夫で、より確度の高い結果が得られるとともに、今後更なる精度の向上も見込まれているが、回答は誤りを含む可能性が常にあり、時には、事実と全く異なる内容や、文脈と無関係な内容などが出力されることもある(いわゆる幻覚(ハルシネーション=Hallucination))。
対話型生成AIを使いこなすには、指示文(プロンプト)への習熟が必要となるほか、回答は誤りを含むことがあり、あくまでも「参考の一つに過ぎない」ことを十分に認識し、最後は自分で判断するという基本姿勢が必要となる。(以下省略)令和5年7月4日 文部科学省 初等中等教育局
『初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン』より一部抜粋
『出力結果は誤りを含むこともあるので、あくまでも”参考程度”に』
…と、令和5年時点の公文書からはそのように言えますが、近年の生成AIはとてつもない速さで進化しており、ハルシネーションもだいぶ減ってきました。また、”どんな情報を基に出力結果を出しているか?”という、ファクトチェック(事実検証または事実確認)を示す生成AIも増えてきています。
(下記の画像はその一例です)

なので、重要な事柄については、ファクトチェックを経て利用しつつも、保育指導案やおたよりの下書き、保育活動の提案などでは『参考程度(=そのまま転載しない)』として利用と、うまく使い分けるのが良いかと思います。
著作権と生成AIについて
生成AI開発時における学習と著作権について
著作権侵害の要件としては「類似性」及び「依拠性」が必要であることから、学習データである著作物と類似したものの生成を防止することで、生成AIの利用による著作権侵害の発生確率を低減させることが可能です(1-2-1参照)。
このような類似物の生成防止措置が施されていること等の、当該生成AI(学習済みモデル)における著作権侵害の防止に向けた取組みに関する情報は、AI提供者にとって、AIサービスの利用規約等において、AI利用者による著作権侵害行為を抑制するための措置等を適切に定める上で重要な情報といえます。
また、生成・利用段階において著作権侵害となるおそれの程度等を踏まえて利用の是非を判断する上で、AI利用者にとっても重要な情報です。そのため、こうした情報は、AI開発者からAI提供者やAI利用者等に対して提供されることが望まれます。
『基本、大丈夫!!(AI開発者・提供者が“適切な知識”をもっていれば…)』
…ということになります。では、その適切な知識をもっているかどうかをどのように確認するか?
『使う前に利用規約等を確認する』
ここに尽きます。特に、業務で利用する際は、必ず確認しておくことをおすすめします。
生成AIを利用した生成物の著作権について
生成AIによる生成自体は、個人が私的使用の目的で生成する場合(著作権法第30条第1項)や企業・団体等の内部において、権利者から許諾を得て利用することを前提に、検討の過程において生成する場合(同法第30条の3)は、これらの権利制限規定の範囲内であれば、権利者の許諾なく適法に行うことができます。
これに対して、AI生成物の利用(インターネットでの配信、複製物の譲渡等)については、
権利制限規定の範囲外となる場合が多いと考えられます。
そのため、AI生成物の生成自体は適法に行える場合でも、生成物を更に利用しようとする場合は、著作権侵害を生じさせないか確認(3-1-5も参照)することが必要です。
著作権侵害の要件としては、既存の著作物との「類似性」及び「依拠性」の双方が必要です。そのため、既存の著作物との関係で「類似性」がないAI生成物については、その利用について、著作権法上、特段の許諾を得ることは不要です。
そのため、AI生成物については、その利用に先立って、まずは既存の著作物と類似していないかを確認することが必要です。
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。(以下省略)著作権法 第三十五条 より抜粋
『AI生成物が類似性・依拠性の双方が成立せず、保育業務内における利用であれば、基本大丈夫!!』
ということになります。
(※ただし、お祭りやバザーの出店で、キャラクターを利用した物を”売る”となった場合や、地域のお祭りや発表会に”報酬を得た上で”参加し、楽曲を利用するといった場合は、念のため法律家の方や著作権を有する権利者の方に、確認しておくことをおすすめします)

ちなみに、当サイトで配布しているVBAツールやファイル(AI生成物)は、そもそも筆者自身が著作権を放棄しているので、安心してご利用ください。
生成過程においても、筆者が試行錯誤して編み出した、独自のプロンプトを経て作成したものなので、「依拠性」はありません。「類似性」に関しては、調べた限りにおいては類似したものはなかったですが、世の中にある書式全てを確認できたわけではないので、”完全に大丈夫です”とは言い切れないのが現状です。ただし、著作権侵害行為の要件としては、「類似性」と「依拠性」の双方が必要なので、片方(「依拠性」がない)が確立されている以上、適法内だと考えております。AI生成物の著作権放棄に関しては、プライバシーポリシーにも明記していますので、一度ご確認ください。
また、ここまで国や官公省庁から出ている資料や法律をもとに、記してきましたが、「なんで保育なのに、厚生労働省やこども家庭庁から出していないんだろう?文科省にしても初等中等局だし…」という疑問をもたれた方、実に鋭いです。
2025年3月現在、こども家庭庁でガイドライン”案”が進んでいますが、それ以上に生成AIの進化が速く、かなりの苦労を伴うこととは想像に難くありません。
今後、保育現場で生成AIを利用する際の”具体例を想定した”ガイドラインのようなものが、策定され次第、このページでも更新・紹介していきたいと思います。
最後に、長々と書きましたが、筆者自身は法律家ではないので、万が一の事が起こった場合やリスクの再検討をしたい場合などは、必ず専門家の方の判断を仰いでください。